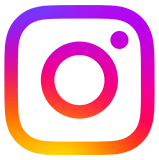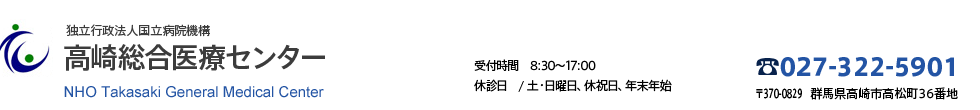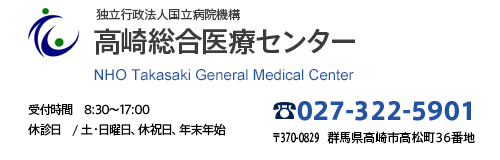治験の3つのステップ
第一相試験(臨床薬理試験)
まず、少人数の健康成人において、ごく少量から少しずつ「くすりの候補」の投与量を増やしていき、安全性はどうかについて調べます。また、血液や尿などの中に存在する「くすりの候補」の料を測ることにより、どのくらいの速さで体内に吸収され、どのくらいの時間でどのように体外に排出されるのかも調べます。
体に現れた変化が「くすりの候補」の副作用かどうかを見極めるため、プラセボ(有効成分が入っていない、見た目や味などの点で「くすりの候補」と区別がつかないもの)を同時に使って比較することもあります。
第二相試験(探索的試験)
次は、「くすりの候補」が効果を示すと予想される比較的少人数の患者さまについて、病気の程度によってどのような効き目を発揮するのか(有効性)、副作用はどの程度か(安全性)、またどのような使い方(投与量・間隔・期間など)をしたらよいか、といったことを調べます。効き目や使い方を調べるに当たっては、通常いくつかの投与量を用いて比較検討しますが、その際にプラセボ(有効成分が入っていない、見た目や味などの点で「くすりの候補」と区別がつかないもの)を加えるのが一般的です。
また、現在使われている標準的な「くすり」がある場合には、それと比較することもあります。
第三相試験(検証的試験)
最後に、多数の患者さまについて、第二層試験の結果から得られた「くすりの候補」の有効性、安全性、使い方を最終的に確認します。
確認の方法は、現在使われている標準的な「くすり」がある場合にはそれと比較、標準的な「くすり」がないときにはプラセボ(有効成分が入っていない、見た目や味などの点で「くすりの候補」と区別がつかないもの)との比較が中心になります。
これとは別に、長期使用したときの有効性や安全性がどうかを調べることもあります。
第四相試験(治験的使用)
「くすり」として承認された後、老人や用事も含めた多くの患者さまが使用してゆく中で、引き続き、新たな副作用や相互作用(他の薬との関係)の調査を目的とした試験です。