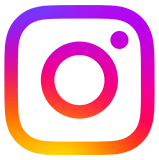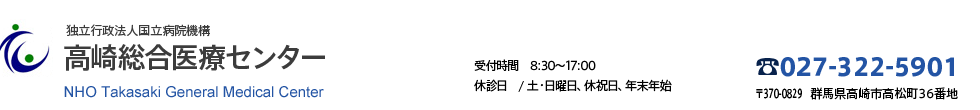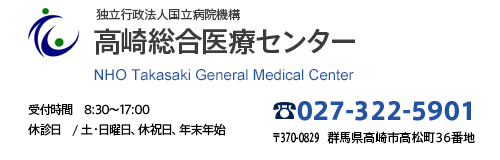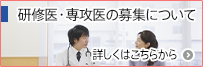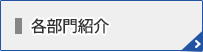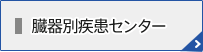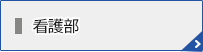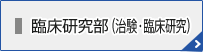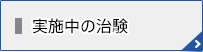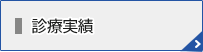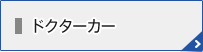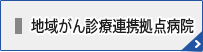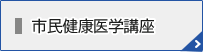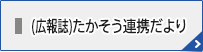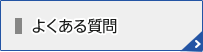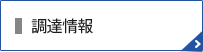2019(令和元)年度 活動の紹介
1. 診療体制
●診療方針
呼吸器科では肺癌をはじめとする腫瘍性疾患(悪性中皮腫、縦隔腫瘍を含む)、慢性閉塞性肺疾患、気管支喘息、多種多様な呼吸器感染症(肺炎、気管支炎、細気管支炎、胸膜炎、肺結核など)、特発性肺線維症をはじめとする間質性肺疾患(特発性間質性肺炎、膠原病肺、薬剤性間質性肺炎など)、各種胸膜炎、肺血栓塞栓症などを主な対象疾患としています。肺癌は現在本邦において悪性腫瘍の死因第1位であり、肺癌の予防と治療は21世紀のわが国の医療が抱える重要なテーマの1つです。肺癌患者の治療は十分なインフォームド・コンセントを得た上で、手術療法、化学療法、放射線療法のうち、その患者に適切な治療法を選択し施行しています。呼吸器内科としては化学療法単独、放射線療法単独、ならびに化学療法・放射線療法併用療法を行っています。近年では、分子標的治療薬や免疫チェックポイント阻害薬の臨床応用により、治療法が大きく変化し、肺癌の治療成績は飛躍的に向上してきています。呼吸器系キャンサーボード(呼吸器内科・呼吸器外科・放射線治療科の合同カンファランス)を毎週1回開催し、最新の肺癌診療ガイドラインを参考にして適切かつ効果的な治療を目指しています。また、緩和医療にも力を注いでいます。
高齢化が一層進む中、慢性閉塞性肺疾患の慢性呼吸不全患者は増加しています。慢性呼吸不全患者の急性増悪症例も多く、救命センターを中心に呼吸器系救急医療を精力的に行っています。
肺炎を代表とする呼吸器感染症は日常診療で遭遇することの多い呼吸器疾患で、特に高齢者の死亡率は高く重症例を含め適切な診断と治療を行っています。
間質性肺疾患としては、特発性間質性肺炎をはじめ、関節リウマチなどの自己免疫性疾患に関連する間質性肺炎も数多く診療しています。特に各種間質性肺炎の重症呼吸不全患者は他院からの転院要請も多く積極的に応じています。
2. 診療実績
●症例数・検査数・治療
呼吸器科入院患者数は、一日平均で、2016年度は39.2人、2017年度は40.8人、2018年度は40.0人でした。平均在院日数は、2016年度は16.2日、2017年度は15.8日、2018年度は15.6日でした。入院患者の主な疾患は、肺癌(52%)、肺炎(25%)、間質性肺疾患(8%)、慢性閉塞性肺疾患・気管支喘息(4%)、呼吸不全(15%)などです。肺癌入院患者延べ492件中、全身化学療法は283件に施行され、分子標的治療薬は16件、免疫チェックポイント阻害薬は30件に導入され大幅な伸びを示しています。放射線治療科の協力により肺癌放射線治療も積極的に行われています。
2019年度の呼吸器科外来の新患数は868人、延べ患者数は年間9,652人と増加傾向が続いています。年間入院患者数は794人、一日平均入院患者数は34人で、疾患別では肺癌が最も多く48%、次いで肺炎(18%)、間質性肺疾患(8%)、COPD/気管支喘息(4%)でした。
2019年度の新規肺癌登録者数は238名と増加し、化学療法実施患者数も年間95人に増えています。特に免疫チェックポイント阻害薬投与患者数は年々増え、2018年度は18名でしたが2019年度は34名と約2倍に増えており、今後もこの傾向は続くものと思われます。
気管支鏡検査は、2019年度は115件行っています。2011年1月より日本呼吸器内視鏡学会認定施設に認定され、2012年度には超音波気管支鏡が導入されました。肺癌患者の増加に従い超音波気管支鏡検査対象患者数は増加しています。 クリニカルパスについては、気管支鏡検査パス、超音波気管支鏡検査パス、CTガイド下生検パスが導入されています。
3. 臨床研究テーマ
1)肺癌化学療法
・間質性肺炎合併肺癌におけるカルボプラチン+アブラキサン療法の有用性の検討
・ペメトレキセートによる長期維持療法の検討
・EGFR-TKI治療中に病勢進行をきたした非小細胞肺癌患者における遺伝子変異検査及び治療方針決定に関する実態調査への参加
・EGFR遺伝子変異陽性非小細胞肺癌患者再発時のT790M耐性遺伝子陽性例の臨床的検討
・EGFR T790M変異陽性非小細胞肺癌におけるオシメルチニブの効果予測因子に関する前向き観察研究
2)薬剤性肺障害の臨床的検討
・抗癌剤による薬剤性肺障害
・分子標的治療薬による薬剤性肺障害
3)関節リウマチ関連
・関節リウマチ患者治療中に起こる呼吸器合併症の臨床的検討
・関節リウマチに合併する呼吸器病変の検討
・抗リウマチ薬使用中に発症するニューモシスチス肺炎の臨床的検討
・メソトレキセートなど抗リウマチ薬による薬剤性間質性肺炎の検討
4)各種間質性肺炎のHRCT所見の検討
・上葉優位型肺線維症の臨床的検討
・DADの臨床病理学的検討
・放射線肺臓炎の臨床的検討
5)肺癌関連
・トルソー症候群を中心とする肺癌合併凝固異常症の臨床的検討
6)乳癌術後胸部接線照射による照射野外に発生する器質化肺炎の臨床的検討
7)呼吸器感染症関連
・レジオネラ肺炎の臨床的検討、肺炎球菌性肺炎との比較検討
・ニューモシスチス肺炎の臨床的検討
・ステロイド・免疫抑制薬治療中におこるニューモシスチス肺炎の予防に関する研究
・ステロイド・免疫抑制薬治療中におこる呼吸器感染症の臨床的検討
-PCP,クリプトコッカス症,細菌性肺炎,結核など-
・肺癌治療経過中に発症した呼吸器感染症の検討
4. 研修教育方針
2020年度診療方針と研修教育方針
スタッフは中川純一部長、増渕裕朗医師、内田恵医師、板井美紀医師の計4人体制に減員となりました。
外来は一日平均40人、入院は一日平均40人、平均在院日数は14日を計画しています。現行の体制では、日々の新患受け入れや、救急・入院患者の対応が難しいため、群馬大学呼吸器アレルギー内科から非常勤医師を派遣していただき、主に外来診療の補助をいただいています。
外来担当は、月曜は中川・佐藤(午後のみ)、火曜は内田・申(群大)、水曜は板井・増渕、木曜は中川・増渕、金曜は内田・若松(群大)が担当しています。新患数は紹介患者を含め年々増加してきており、今後益々増加することが予想されます。また、病診連携を深めて積極的に逆紹介も増やしていきます。
毎週火曜日に北5階病棟で呼吸器カンファレンスを行い、毎週木曜日には呼吸器系キャンサーボードを開催しています。また、群馬大学医学部附属病院と公立藤岡総合病院との呼吸器疾患合同カンファランスを3ヶ月に1回行っています。
今後は研修医教育には一段と力を注ぎ、当院を魅力のある病院にするべく努力していきたいと考えています。
5. 今後の展望
群馬大学附属病院をはじめとする他の専門病院との連携を深め、県内の呼吸器科医の育成に努め、呼吸器疾患診療のさらなる充実を目指します。