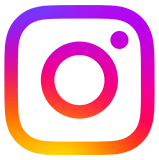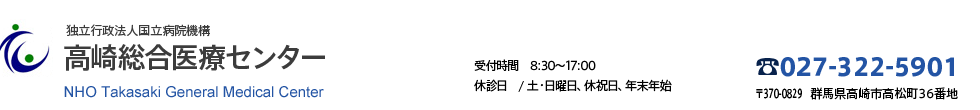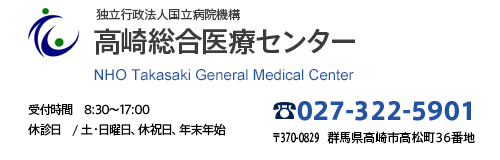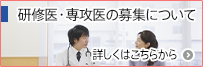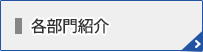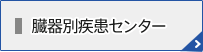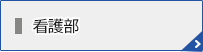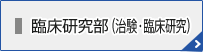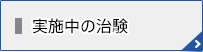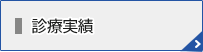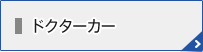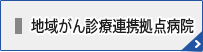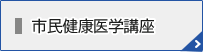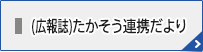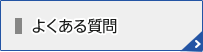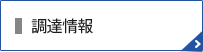2023(令和5)年度 活動の紹介
1. 診療体制
●診療方針
西毛地区で唯一の救命救急センターを有し、地域がん診療連携拠点病院としての機能を果たす当院において、当科は自殺企図への介入、がん患者のメンタルケアを中心に総合病院におけるいわゆる精神科リエゾンの実践の場となっております。
ここ数年当施設に自殺企図で搬送された方(既遂は除く)の傾向としては、10代~30代の若い世代が年々増加傾向にある、ICD-10の F3(気分障害)と F4(神経症)の比率が高い、女性の比率が高いといったものがありますが、各ケースに真摯に取り組むことが、我が国における自殺に関する課題(例えば若い世代の自殺)への解決につながっていくものと考えております。また、自殺企図で搬送された方(既遂は除く)で明らかな精神疾患を認めない方も約10%(約10人に1人)おり、家庭問題・経済的問題・勤務問題など多種多様な背景への支援も重要であると日々実感しております。MSW(メディカルソーシャルワーカー)などと多職種連携しながらよりよい診療に取り組む所存です。
がん患者のメンタルケアにおいては、主にせん妄やうつ状態が課題となっており、院内のチームと連携しながらハイリスク評価と、防止対策を実施し、発生時には適切な治療を行うようにしております。治療にあたっては、常に最新の医学知識を取り入れ、特に向精神薬については適切な使用を心がけております。
その他、身体合併症のある精神疾患(当院は精神病床がないため一般病床入院中に介入)、周産期のメンタルケアなど、総合病院精神科ならではの診療も行っております。
なお、専攻医への指導(群馬大学医学部附属病院精神科専門研修プログラム、群馬県立精神医療センター精神科専門研修プログラム、群馬病院精神科専門研修プログラムの三つで当科が連携施設となっている)、研修医への指導(1年目研修医は精神科が1ヶ月必修。2年目研修医も希望者を受け入れている)、特定行為研修生(看護師)への指導、高崎総合医療センター附属高崎看護学校講師なども行っており、後進の育成を通して、地域の精神科医療がより良くなることへ貢献したいと考えております。
●医療設備
脳波(生理検査室)
CT、MRI、SPECT(放射線診断部)
2. 臨床研究のテーマ
○無床総合病院精神科の役割に関する研究
○自殺未遂者の実態調査
○せん妄の実態調査
3. 研修教育方針
日本精神神経学会精神科専門医制度における研修施設である。(施設番号210024)
●目的
総合病院においてメンタルヘルスケアを必要とする患者に対して標準的な専門治療を提供できるための知識や技能を習得する。
●主たる研修目標
<1>総合病院精神科医を特徴付ける能力
- 医療及び地域連携について理解し、実践できる。
- 他職種との連携を行いながら、チーム医療の一因として役割を果たすことが出来る。
- 身体疾患およびその治療を考慮しながら、適切な精神医学的診断が下せる。
- 身体疾患およびその治療を考慮しながら、適切な精神科的治療マネージメントが実行できる。
<2>総合病院精神科医に必要な医学的知識と技術
- 身体合併症を有する精神疾患について適切なマネージメントが行える。
- 各診療科からのコンサルテーションへ適切にマネージメントが行える。
- 自殺企図患者に対して身体科医と連携して適切にマネージメントが行える。
- 緩和ケアについて理解し、緩和ケアチームの一員として機能できる。
<3>すべての精神科医に共通して必要な能力
- 必要な関連法規を理解し運用できる。
- 患者および医療スタッフの安全を守り、危機管理に対する態度を身につける。
- 適切な精神科的面接、診察、検査結果に基づき、精神医学的診断が下せる。
- 適切な精神科的治療法を選択すると共に、経過観察によって、診断および治療を適切に修正改善することができる。
<4>
- 医学研究について理解し、リサーチマインドをもって診療を行える。
- 医学教育について理解し、医学生や初期研修医に対して教育的役割を果たすべく研鑽を積むことが出来る。
4. 今後の展望
西毛地区における中核的総合病院にある精神科として、自殺企図への介入、がん患者のメンタルケアを中心に、引き続き質の高い精神科リエゾンを継続していきます。また、常に知識の向上に努め、より良い精神医療を実行していきます。